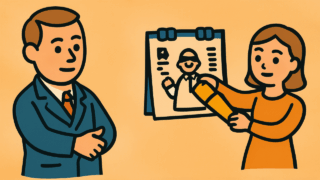 ことわざ
ことわざ 上手は下手の手本、下手は上手の手本の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
上手は下手の手本、下手は上手の手本の読み方じょうずはへたのてほん、へたはじょうずのてほん上手は下手の手本、下手は上手の手本の意味このことわざは、上手な人は下手な人の見本となり、下手な人もまた上手な人にとって学ぶべき手本となるという意味です。...
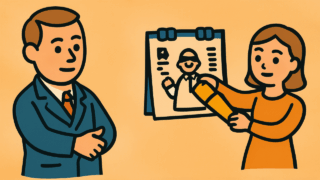 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 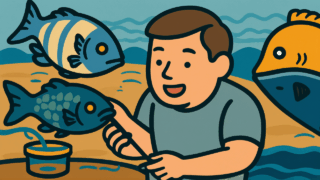 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ