千里の馬も蹴躓くの読み方
せんりのうまもけつまずく
千里の馬も蹴躓くの意味
このことわざは、優れた能力を持つ者でも失敗することがあるという意味を表しています。千里を走る名馬のように、どんなに才能があり、実績を積み重ねてきた人でも、ちょっとした油断や予期せぬ事態で失敗してしまうことがあるのです。
このことわざを使う場面は主に二つあります。一つは、優れた人が失敗したときに、その人を慰めたり、失敗は誰にでも起こりうることだと理解を示すときです。もう一つは、能力のある人への戒めとして、油断や慢心を戒めるときに使われます。
現代でも、スポーツ選手が大事な試合でミスをしたり、優秀なビジネスパーソンが判断を誤ったりする場面で、この表現は生きています。完璧な人間などいないという現実を、優しく、そして厳しく教えてくれることわざなのです。
由来・語源
このことわざの由来について、明確な文献上の初出は定かではありませんが、言葉の構成から興味深い背景が見えてきます。
「千里の馬」とは、一日に千里もの距離を走ることができる名馬を指します。古代中国では、このような優れた馬は非常に貴重で、王侯貴族だけが所有できる宝物でした。千里という途方もない距離を走れる馬は、まさに完璧な能力の象徴だったのです。
「蹴躓く」は「けつまずく」と読み、足を何かにひっかけてよろめくことを意味します。現代では「つまずく」という言葉が一般的ですが、古くは「蹴る」と「躓く」が組み合わさったこの表現が使われていました。
このことわざが生まれた背景には、完璧に見える存在でも予期せぬ失敗をするという、人間社会の観察があったと考えられます。どんなに優れた名馬でも、小石一つ、わずかな段差一つで足を取られることがある。その姿は、能力の高さと失敗の可能性が決して無関係ではないことを教えてくれます。日本に伝わってからは、武士や学者など、優れた人物への戒めとして、また失敗した人を慰める言葉として使われてきたという説があります。
豆知識
このことわざに登場する「千里の馬」は、実際には一日で約4000キロメートルを走ることになり、物理的には不可能です。しかし古代では、この誇張された表現こそが、比類なき優秀さを表す最高の褒め言葉でした。現実を超えた理想の存在を描くことで、かえって教訓の普遍性が高まったと言えるでしょう。
「蹴躓く」という言葉には、単なる失敗以上の意味が込められています。足を「蹴る」という動作が含まれることで、自分から積極的に動いているからこそ起こる失敗というニュアンスがあります。じっとしていれば躓くことはない。挑戦するからこそ、失敗の可能性も生まれるのです。
使用例
- 彼は業界トップの営業マンだったが、千里の馬も蹴躓くで、今回の大型契約は逃してしまった
- オリンピック金メダリストでも千里の馬も蹴躓くというから、私たちが失敗するのは当然のことだ
普遍的知恵
このことわざが何百年も語り継がれてきた理由は、人間の心の奥底にある二つの真実を突いているからです。
一つは、完璧への憧れと、完璧になれない現実との葛藤です。私たち人間は、常により優れた存在になりたいと願います。努力を重ね、技術を磨き、経験を積んで、いつか完璧な自分になれると信じています。しかし現実には、どれほど優れた人でも失敗します。このことわざは、その避けられない真実を、千里を走る名馬という美しい比喩で教えてくれるのです。
もう一つは、失敗に対する人間の複雑な感情です。優れた人が失敗すると、私たちは安心すると同時に、同情も覚えます。「あの人でさえ失敗するのだから」という思いは、自分の失敗を許す慰めになります。一方で、能力のある人への警告としても機能します。油断は誰にでも訪れ、その瞬間に長年の努力が水泡に帰すこともある。
このことわざが示しているのは、人間の不完全さを受け入れる知恵です。完璧を目指しながらも、失敗を恐れすぎない。失敗したときには、それを人間らしさとして受け止める。この絶妙なバランス感覚こそが、先人たちが私たちに残してくれた宝物なのです。
AIが聞いたら
千里を走る名馬が躓くのは、単なる不運ではなく、高性能システムに内在する構造的な問題だと考えられます。複雑系科学の正常事故理論では、システムが高度化すればするほど、予測不可能な失敗が必然的に起きると説明します。
名馬を高性能システムとして見ると、興味深い特徴が浮かび上がります。速く走るために筋肉、神経、呼吸、バランス感覚など多数の要素が極限まで最適化されています。つまり、各部分が密接に連動し、余裕のない状態で動いているのです。社会学者チャールズ・ペローが分析した原発事故やスペースシャトル事故と同じ構造です。個々の部品は完璧でも、AとBとCが特定のタイミングで重なった瞬間、誰も予想しなかった連鎖反応が起きてしまう。
普通の馬なら問題にならない小石も、時速60キロで疾走する名馬には致命的です。高速走行中は一歩の着地時間が0.1秒以下。この瞬間に路面の凹凸、筋肉の微細な疲労、風向きの変化が重なれば、制御不能な躓きが発生します。性能を極限まで高めた代償として、システム全体が予測不可能な組み合わせ失敗に対して脆弱になる。これが正常事故理論の核心であり、このことわざが千年前から指摘していた真実なのです。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、謙虚さと寛容さの大切さです。
あなたが今、何かの分野で優れた成果を上げているなら、このことわざは大切な警告です。成功が続くほど、私たちは無意識のうちに油断します。「これくらいは大丈夫」という小さな気の緩みが、思わぬ失敗を招くのです。だからこそ、どんなに実績を積んでも、基本を大切にし、一つ一つの仕事に真摯に向き合う姿勢を忘れてはいけません。
一方で、もしあなたが誰かの失敗を目にしたとき、このことわざは優しい視点を与えてくれます。優れた人の失敗を見て、批判するのではなく、「誰にでも起こりうることだ」と理解する。その寛容さが、より良い社会を作ります。
そして最も大切なのは、自分自身の失敗への向き合い方です。失敗したとき、「自分には能力がない」と落ち込む必要はありません。千里の馬でさえ躓くのですから。大切なのは、立ち上がってまた走り出すこと。失敗は終わりではなく、次の成功への通過点なのです。
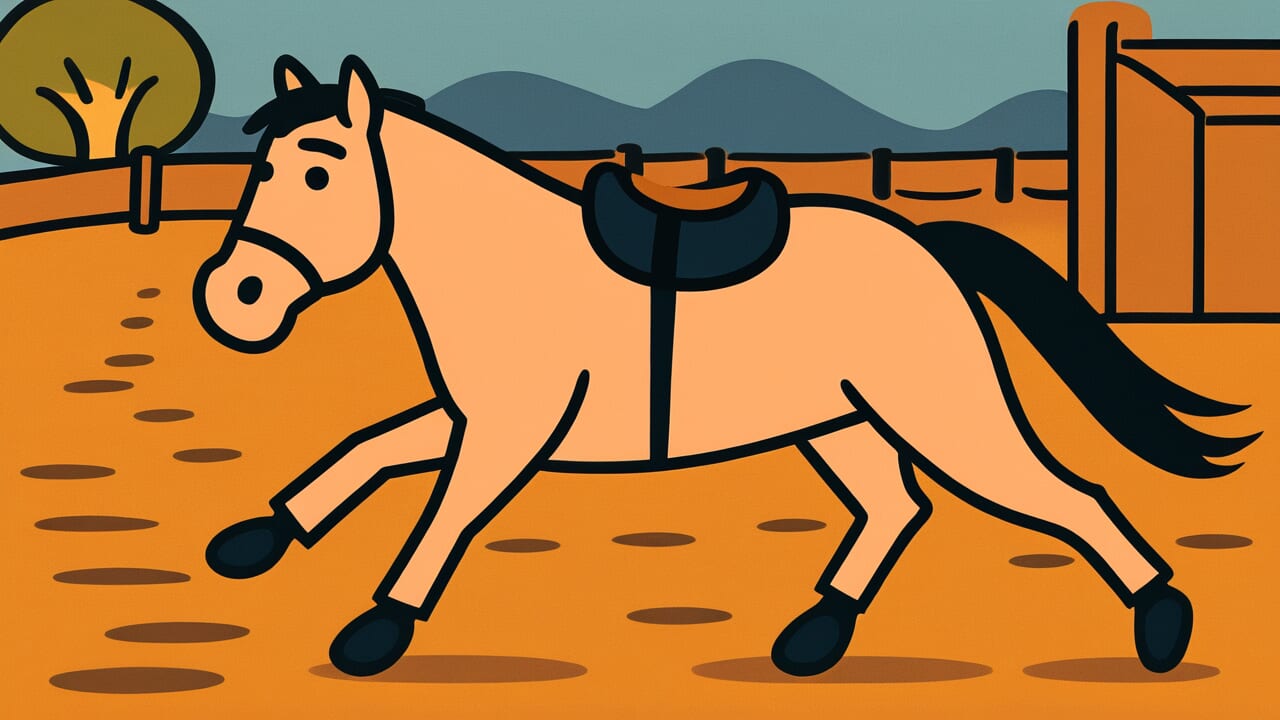


コメント