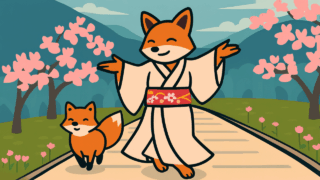 ことわざ
ことわざ 狐の嫁入りの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
狐の嫁入りの読み方きつねのよめいり狐の嫁入りの意味「狐の嫁入り」とは、晴れているのに雨が降る天気雨の現象を指すことわざです。この表現は、日常では起こりにくい不思議な現象や、一見矛盾しているように見える状況を表現する際に使われます。晴天と雨と...
語源・由来・使い方からAI考察まで──どこよりも深く、楽しみながら文化も学べる。英語圏とアジアのことわざ・名言を収録。
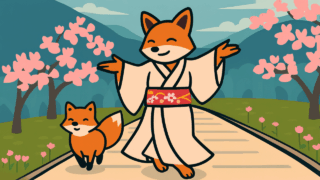 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 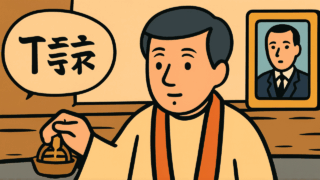 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ